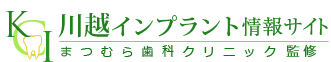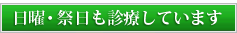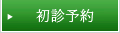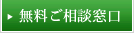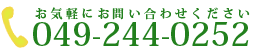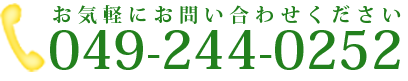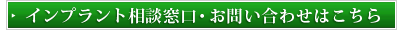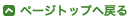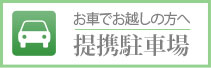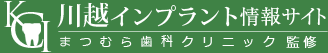インプラントの保険適用はいつから?どうして自費?
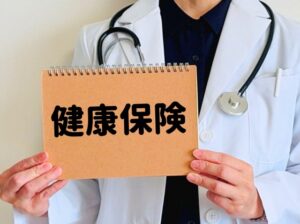
皆さん、こんにちは。川越のまつむら歯科クリニックです。
歯を失ったときの治療法として「インプラント」は多くの患者さんから注目されています。しかし「インプラントは保険でできないの?」と疑問に思われる方も少なくありません。この記事では、インプラントが保険適用にならない理由と、自費診療である背景をわかりやすく解説します。
インプラントは保険適用されない
まず大前提として、インプラントは健康保険の対象外です。これは過去も現在も同じであり、今後も保険適用される予定はありません。厚生労働省が定める保険診療は「最低限度の機能回復」を目的としているため、失った歯を補う方法としては入れ歯やブリッジが対象になっています。
一方、インプラントはチタン製の人工歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工歯を装着する高度な治療法です。見た目や噛み合わせの自然さ、歯茎との調和などに優れますが、機能回復以上に「生活の質(QOL)の向上」を重視している点から、現行の保険制度では対象外とされています。
患者さんにとって「保険でできるなら選びたい」と思うのは自然ですが、インプラントはあくまで自費診療で受けるものと理解しておく必要があります。
インプラントが保険適用にならない理由
1. 医療制度上の位置づけ
日本の健康保険は国民全員が最低限度の治療を平等に受けられるよう設計されています。入れ歯やブリッジで「噛む機能」を回復できると判断されるため、より先進的で費用のかかるインプラントは対象外となっています。
2. 高度で専門性の高い治療
インプラントは外科手術を伴い、骨の状態や歯茎の健康状態によって成功率が変わる治療です。CTによる診断や専用機器を用いた精密な手術が必要で、歯医者による専門的な技術が求められます。こうした点から「標準的な治療」とは位置づけられず、保険の範囲に含まれていません。
3. 費用と制度のバランス
もしインプラントが保険適用になれば、医療保険財政に大きな影響を与えます。インプラントは1本数十万円かかる治療であり、多くの患者さんが希望した場合、国の医療費負担は膨大になります。そのため制度上も現実的ではなく、今後も適用予定はありません。
4. 適応範囲の広さと個別性
患者さんごとに骨の量や全身の健康状態が異なるため、治療内容も大きく変わります。こうした「個別性の高い治療」は全国一律の保険診療にはなじまず、自費診療として扱われているのです。
まとめ
インプラントは「保険でできないの?」とよく質問をいただきますが、現在も将来も保険適用される予定はありません。理由は、入れ歯やブリッジで最低限の噛み合わせ回復が可能であること、医療費の負担が大きいこと、そして治療の専門性が高く個別性が強いことにあります。川越で歯医者をお探しの方には、インプラントの特徴や費用をしっかり理解したうえで、治療の選択肢として検討していただくことをおすすめします。